【自己紹介】大学を中退し、1年間の予備校生活を経て医学部を再受験し関東国公立医学部を含む4校の医学部医学科に24歳で合格したえびまるです。
今回は医学部再受験でのモチベーションの保ち方について、自分の体験や再受験生との関わりをもとにお話ししていきたいと思います。再受験を考えている方の中には、受かるかわからない不安に襲われ、モチベーションが上がらず勉強が疎かになってしまったり、そもそも医学部受験をやめてしまおうかと考えてしまったりする人も多いのではないでしょうか。
①退路を断つ
モチベーションの保ち方についてこの先もいくつか述べますが、ほぼこれに尽きると思います。「退路を断つ」、すなわち「危機感を持つこと」です。人間というものは本来怠惰な生き物です。自分の安全が守られていれば、別に新たに何かをする必要はありません。現状維持でいいのです。学生時代の試験前を思い出してください。自分の中でまだ勉強に本腰入れなくても大丈夫だと思っているときは、漫画を読んだりネットサーフィンしたりする余裕がありましたよね。しかし、本当に直前になると焦って試験直前までずっと勉強することができたと思います。
とはいえ危機感を持つ基準というのは人それぞれです。まず、私の場合について書きたいと思います。
ブログのタイトルや冒頭にも述べましたが、私は医学部に行きたくて、通っていた大学を中退しました。晴れてニートです、しかも23歳で。もし同じような経験した人がいたら、これくらいの年齢で自分の肩書きが何もないことの惨めさに共感してくれるのではないでしょうか。中高で一緒だった優秀な友人たちは、有名な大企業で働いていたり、順調に医学部での生活を謳歌していたり、院に進んでいたり・・・。その一方、私は医学部受験をすると言って何も成し遂げていないただのニートです。親に迷惑と心配をかけるだけの存在。娘がニートだなんて、恥ずかしい思いもさせたと思います。中学受験は成功したのに、なんでこんなことになったんだろうと、落ちるところまで落ちた気分でした。
でもここまで落ちたからこそ、何が何でも医学部に受かってやると思うことができました。実は私は再受験前に在籍していた大学で仮面浪人のようなことも少ししていたのです。しかし、うまくモチベーションを保てず挫折してしまいました。大学の授業や試験勉強もありましたし、私が仮面浪人をしているなんて知らない友達は遊びに誘ってくれます。誘惑に負けてしまい、遊ぶことも多々ありました。もちろん意志が強ければ、断って受験勉強できたでしょう。しかし、結果として私は大学を中退して後がない状況になるまで本気で取り組むことはできませんでした。
私以外の例も挙げたいと思います。予備校で出会った27歳女性のAさんは企業に勤めていましたが医学部に行きたいと一念発起し会社を辞め、これまでの貯金で予備校に通い、関東圏の国公立医学部に合格されました。同じく予備校で出会った私の25歳の男性Bさんは、有名大学の理系学部の院を卒業した年に予備校に入り同じく関東圏の国公立医学部に合格していました。さらに私が大学で出会ったCさんは有名大学の理系学部を卒業した年に卒論と並行して医学部受験もして合格したそうです。Cさんは元の大学に在学中も3度ほど医学部を受験をしていたそうですが、いよいよ卒業になる年に危機感を感じて勉強が捗ったと言っていました。みんなに共通していることは、それぞれにとって後がない状況であるということです。
先ほど述べたように、危機感を抱く基準は人それぞれです。私みたいに肩書がない状態まで自分を追い込まないとできない人もいれば、社会人として働いたりや大学生活を送ったりしながらでも危機感を持って勉強に取り組める人もいるでしょう。自分がどの段階まで行けば危機感を持つのか把握するのが大事だと思います。
②同じ志を持った人が集まる場所に行く
私にとって、予備校がその場所でした。医学部専門の予備校は、通っている人のほとんどが医学部を目指しています。同じ志を持った人が周りにいることで、自分も頑張ろう、負けたくないと思えます。
また予備校で友人を作ることもモチベーション維持の方法の一つだと思います。再受験をする人の多くは、高校からの友人や知人がおらず、一浪や二浪の人たちとも年齢が少し離れているため自ら声をかけなければ友人はできないかもしれません。しかし、勇気を持って友人を作ることで、受験に関する情報交換ができたり、勉強の合間に話すことでリフレッシュできたりすると思います。
私はもともとあまり自分から友達を作りに行くのが得意ではないため、予備校入学とともにTwitterで受験の情報収集用のアカウントを作っていました。予備校に入って1か月くらいして、Twitterを通じて同じ予備校の人から会わないかと言われました。会うか迷いましたが、なにかのご縁だと思って会うことにしました。そこから何人か友達もでき、自分の中でも良いモチベーションになって結果的には良かったと思います。
しかし友達作りやSNSには、注意しなければならない点もあると思います。まず、人間関係です。私はありませんでしたが、人間関係のトラブルや恋愛で意識がそちらに持っていかれてしまう人もちらほら見受けられました。また、SNSもやりすぎには注意です。私はSNSに気を取られて勉強が疎かになってしまうことも多く、かなり反省しております。ちなみに現在医学生になってSNSは時間の無駄だと思って、TwitterもインスタグラムもFacebookもログアウトして見ていません。そろそろアカウントごと消してもいいかなと思っています。
③自分の目標を見失わない
自分の本当にしたいことが何か、日々確認することです。私は医学に興味があり、医学部に入って医学を学びたいという気持ちが強かったので、そこがぶれることはなかったと思います。もし自分の人生を見つめなおしてみて、自分が本当に求めていることが医学部に入ることじゃないならば、再受験をやめたっていいと思います。例えば、お金持ちになることが本当になりたい自分で、医学にちっとも興味がないとしたら、医学部に入って医者になる必要なんかないですよね。
でももし本当に医者になりたいんだとしたら、その目標に向かって走るべきです。そのために逆算して日々計画的に勉強するのが良いと思います。今は夏だから基礎の復習をするとか、秋は過去問解こうとか。一日、一週間、一か月、数か月単位で計画を立てるのがお勧めです。計画というものはやっていくうちにどんどん修正されると思いますが、漫然と勉強するのと比べ勉強の効率が段違いに良いです。人間、ゴールが見えると俄然やる気が出る生き物なのです。
④ルーティン化する
習慣というものは、とても奥が深いので簡単にルーティン化できるとは言えないのですが、それでも続けていったら身につくし、ルーティン化することで勉強のハードルが下がると思います。私は毎日同じような生活サイクルを送ることを心掛けていました。毎朝同じ時間に起き、顔を洗ってコーヒー飲んで朝食を食べ、5分でメイクして、予備校のいつもの自習室に行く。そして同じ時間に帰って寝る。これを一年間通してやりました。自習室ではスマホを触らないというルールも作っていたので自習室に入る前に毎回電源も切るようにしていました。ルーティンというのはいつもやっていることだから、新しいことをやる場合と比べて使うエネルギーが少ないし、抵抗感も少ないです。勉強を始めるまでに使うエネルギーが多いとそれだけで疲れてしまいますよね。ルーティンを作ることで、やる気の波にとらわれずに勉強することができます。よく言われることだと思いますが、勉強を始める前にはやる気が出なくても、一旦勉強を始めてしまえば案外ずっとできるものです。最初の勉強のハードルを下げるためにルーティン化はとても有用だと思います。
ここから先は勉強のモチベーションとは少し関係ないのですが、自分が試験前にやっていたルーティンとその効果をご紹介したいと思います。私は試験の日は毎回試験会場に30分ほど前に到着するようにし、毎回同じエナジードリンクを飲むようにしていました。また、試験の合間は一科目ごとに必ずお手洗いに行くようにしていました。スポーツ選手が競技前にするルーティンなどが時々話題になると思いますが、ルーティンをこなすことで緊張しすぎず適度な緊張と落ち着きをもって、試験に臨めたと思います。もちろんルーティンの効果を明確に証明できるわけではないのですが、再受験のときの入試結果は今まで受けたどの年の入試結果より良かったし、難しい科目の試験があっても次の科目では切り替えて試験を受けることができました。
このように、ルーティンは勉強へのハードルを下げるだけでなく、パフォーマンスも上げる効果があります。
今振り返って、自分のモチベーション維持で重要だと思ったことをピックアップしてみました。参考になれば幸いです。また思いつけば追記しますね。
X(旧Twitter)始めました▶︎@ebimaru_saijyu


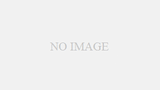
コメント