【自己紹介】大学を中退し、1年間の予備校生活を経て医学部を再受験し関東国公立医学部を含む4校の医学部医学科に24歳で合格したえびまるです。
医学部受験で合格するには、勉強や面接対策など様々なポイントがありますが、今回は勉強法に焦点を当てたいと思います。まず初めに、私は1年間予備校に通っていたので、独学で再受験を目指している方や社会人で働きながら勉強されている方には参考になる部分は少ないかもしれません。しかし、私が予備校の名だたる先生から聞いた勉強への取り組み方や各時期ごとに取り組むべき内容などは参考になることも多いと思うので良かったら読んでください。
①【4月から夏まで】とにかくまずは基礎固め!
これは予備校の初回の授業でほとんどすべての先生が言っていたことです。
そもそも基礎とは?何するの?
私の中での基礎固めができている状態とは、「教科書レベルをスラスラ解けるようになっている状態」のことです。数学で言えば、教科書に載っている定理の導出が自分でできる、その定理を使った簡単な問題が解ける、用語の定義がちゃんとわかっているなどです。例えば、三角形の重心、外心、内心、垂心、傍心、すべての定義をスラスラ言えますか?積和の公式を導出できますか?こういったことがそもそもできていないと、例えば垂心を用いた問題を解くことすらできません。私も再受験の勉強をし始めた時は全然覚えていなくてかなり焦りました。
なぜそんなにも基礎固めが大事なのか?
勉強というものは基礎という大きな土台があって、その上に応用を積み重ねていくものです。土台がしっかりしていないうちに応用を重ねて一時的に成績が上がったとしても、土台が穴ぼこだらけならそのうち崩れてしまいます。模試で応用的な問題が解けなかったり、周りが難しそうな問題集を解いていると、不安になり自分も早く応用問題を勉強しなければいけないのではないかと焦ることもあると思います。しかし長い目で見たら最初に堅実に基礎固めをすることが合格への近道になります。
私の知人の話も紹介したいと思います。彼は千葉大医学部に現役で受けるも、ほとんど勉強していなかったためセンター試験の足切りにあってしまい2次試験を受けることすら叶いませんでした。しかし、浪人中に周りが難しい問題を解く中で、一人数学の教科書の問題を完璧にすることにして基礎を固めた結果、数学では最上位の結果を取るようになり、他の人にも教えるレベルにまでなったのです。そして一年の浪人の末、千葉大医学部に合格しました。
ではどれくらいの期間基礎固めをすれば良いのか?
多くの予備校の先生が言っていたのは夏まではしっかり基礎固めをするということです。もちろん人それぞれ勉強の進捗は異なるので一概には言えません。例えば、文系から理転して理科を一からやり直す場合や受験そのものが久しぶりである場合はもっと基礎固めにもっと時間を要すると思います。昨年度惜しくも受験に失敗してしまった場合でも基礎が疎かになっていないか夏まできちんとやり直すことはとても重要だと思います。
私が通っていた予備校の場合、数学は特に前期は基礎、後期は応用となっていました。授業後に毎回その授業の復習をしつつ、夏休みに前期のすべての範囲の復習をしました。理科は、通年を通して範囲がカバーされていたので前期は基礎固めという意識が薄かったのですが、定期的に全体を復習することを心掛けました。科目ごとの具体的な勉強法は長くなってしまいそうなのでまた別記事を作りたいと思います。
②【夏から共通テスト1か月前まで】復習と応用と大学の過去問演習
後期が始まって予備校の授業とその予習復習に加え、定期的に前期の授業を見返したり、(主に私大の)過去問を解いたりする作業も増えたので前期よりさらに忙しかったように思います。過去問演習では、難関私大は難しい問題が解けなくて目標点に届かず落ち込むこともありましたが、基礎的な問題を多く出してくれている大学では手ごたえもあり、基礎固めの効果を実感するとともにこのままいけば合格できるかもという感覚も得ることができました。
共通テスト対策では記述して問題演習をすることが少なくなるので、この時期はたくさん手を動かして勉強することを心掛けました。
③【共通テスト1か月前から共通テストまで】
科目によって若干対策を始めた時期が異なるのですが、大体の科目で共通テスト1か月前に共通テスト対策をしたと思います。社会は地理選択だったのですが点数が安定せず不安だったため1か月以上前から、参考書を予備校の行き帰りの電車で読んでいました。共通テスト前は地理に最も時間を割き、問題演習も一番したにも関わらず72点しか取れなかったので、倫理政経など勉強すれば安定して高得点をとれる科目にするべきだったかもしれません、、。
共通テストの過去問は一年分しかないので、予備校2か所くらいの予想問題パックをすべて解きました。センター試験の過去問も解きました。特に数学と理科と地理とリスニングを多く解きました。
④【共通テスト後から国公立医学部受験まで】
共通テスト後は自己採点をした後、真っ先に微分積分の簡単な問題を数百問解きました。予備校の先生がまとめてくれたプリントを事前に配布してくれておりそれを淡々と解きました。初めの方は解くのに少し手間取ってしまい、数Ⅲに1か月近く触れていないとこんなにも衰えるのかというのを感じました。
共通テストの数日後には最初の私大受験である国際医療福祉大学の受験が控えていたので、事前に過去問演習はしていましたが、もう一年解いて受験の感覚を掴みました。
この後は私大の一次試験と受かったときの面接対策、私大の二次試験がいくつも入り、丸一日落ち着いて勉強できる日は国公立医学部受験まであまりなかったように思います。合格発表もたくさんあり緊張と不安の日々を過ごしていました。幸いにも、国公立までにいくつか私大の合格をいただき、落ちた大学も一次試験は突破できたのである程度学力はあるのではないかという自信をもって国公立の受験に挑むことができました(慶應医学部は一次落ちでしたが、感触からして落ちてそうだと思っていたのと、国公立の受験の後に見たのでそこまでショックはなかったです)。私大受験の合間は国公立の対策をメインに行い私大受験前はその学校の対策を行っていました。そして無事に国公立医学部に合格することができました。
参考までに私の受験結果を載せておきます。
国際医療福祉大学 一般選抜 正規合格
国際医療福祉大学 センター利用 正規合格
東邦大学 正規合格
日本医科大学 前期試験 一次合格 二次不合格
順天堂大学 補欠落ち(補欠が回ってきませんでした)
東京慈恵会医科大学 正規合格
慶應大学 一次落ち
国公立 正規合格
ここまで読んでくださりありがとうございました。また再受験の間のモチベーション維持やさらに具体的な勉強方法、面接対策についてブログを上げていくので良かったら覗いていってください。
X(旧Twitter)始めました▶︎@ebimaru_saijyu


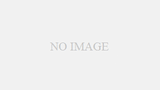
コメント