【自己紹介】大学を中退し、1年間の予備校生活を経て医学部を再受験し関東国公立医学部を含む4校の医学部医学科に24歳で合格したえびまるです。
今回は医学部再受験において、私が行った願書の対策をお伝えします。医学部受験は他学部とかなり異なる特徴を持っています。医学部受験では、就活のエントリーシートのように、経歴や短所、長所、弊学志望理由など願書を出す際に書かされる場合が多いです(特に私大では項目が多いイメージ)。このようなことをさせるのは、医学部受験には面接があるから!願書の対策は大きく見ると面接対策にもなりますが、面接対策そのものは直前期でも良いと思うので、また別記事にします。今回、「願書」という部分にフォーカスを当てたのは、特に再受験生は願書をよく見られるからです。なぜ再受験生は願書をよく見られるかというと、再受験生は現役生に比べ年相応の経歴や成熟性を求められるからです。多少受け応えが下手でも高校生だと多めに見てもらえる事がありますが、再受験生ではそうはいきません。理路整然と落ち着いた受け応えができてなければ、容赦なく減点ないし不合格になってしまうかもしれません。現役生と再受験生が同じくらいの受け応えだったり同じような経歴だったりしたら、当然現役生が選ばれますよね。
また、願書に書ける内容は直前期になって慌ててできるものではないです。早めから行動を起こして、資格欄やアピールポイントとして書けることを準備しておくことが大切です。
以下、私が願書対策のためにしたことをご紹介したいと思います。何もない状態でも一年あれば余裕で取れるものなのでかなりおすすめです。
①英検準一級
私は英検準一級を取得しました。通っていた予備校の先生に、資格欄にかけるのは英検準一級以上だねと言われたので、取りました。もちろん英検一級やTOEFLでの高得点などもっと難しい資格が取れる方は、そちらの方が良いです。私は受験英語のリーディングは得意だったものの、ライティングにそこまでの自信はなく、リスニングやスピーキングに至ってはかなりの苦手だったので一級ではなく準一級を目指すことにしました。英検だけに集中すれば一級も目指せたかもしれませんが、他にもたくさんやりたい勉強があったので、少しの背伸びで届く準一級を受験することに決めました。下の写真が一次試験の結果です。



見ていただいたら分かると思いますが、リーディングで稼いでなんとかリスニングのビハインドを埋めていますね。ライティングも合格ラインギリギリです。とはいえ、一次試験に合格したので二次試験を受験する資格を得ることができました。しかし、このままスピーキングの試験を受けると確実に落ちると思い、英検のスピーキング対策をしてくれる英会話教室に数ヶ月ほど行くことにしました。頻度は週に一回でしたが、毎週英検対策を教えてもらい、日常生活でも「この動作は英語でなんて言うか」などと考えることにより対策をしていました。不思議なことに普段からきちんと英検の練習をしているかということは、英会話を生業としている先生にはバレるものです。英会話教室の先生にも普段から英検で聞かれたらなんと答えるか考えるようにしましょうと言われていたのですが、少しサボって練習しなかった週は英語力が伸びず「練習してなかったでしょう」と言われ、ちゃんと練習をして臨んだ授業では褒められるのです。先生のおかげで、苦手だったスピーキングも英検までになんとか間に合いギリギリ受かることができました。以下二次試験の結果です。

なんとか、ギリギリですが合格しました。確か英検は、一次の筆記試験が受かっていれば二次試験が何回か受けられるはずですが、一発で合格してよかったです。頑張れば一回で受かるものを何度も受験するのは時間も労力もお金も無駄にすることになると思い、気合いで乗り切りました。(この言葉を現役時代の自分に言い聞かせたいものです…)
②上級救命認定証
上級救命認定証は上級救命講習を受講し実技と筆記試験に合格することで取得することができます。この講習は全部で8時間でその日のうちに修了証をもらうことができます。長丁場ではありますが、英検のように事前に勉強する必要もなく基本的に受ければほとんどの人が合格し(私が受けた際は20人ほどいて全員合格でした)、願書の資格欄にも書くことができるのでぜひ受講することをおすすめします。医療系の資格なので、有事の際に救命することができますし、自分がそのような意思を持っていると面接官に示すことができます。資格を持っていなくともアピールすることは可能ですが、資格があった方が説得力も増しますよね。
上級救命講習は、成人の心肺蘇生法、AEDの使用法、気道異物除去法を学ぶ普通救命講習の内容に加え、小児・乳児の心肺蘇生法、外傷の手当てなどプラスアルファの内容を学ぶことができます。
有効期限は3年間なので、以前取得したことがある人で入試の際に期限が切れてしまう人は3時間ほどの再講習を受けるのが良いと思います。
注意点としては、この講習には人数制限があるため、自分の行きたい日付に空きがないことが多々あるということです。私も結局、自分の家の近くには空きがなく自宅から遠い消防署で講習を受けました。さらに思っていた数ヶ月先に受講することになり、日程調整にも苦労しました。早めからこまめにチェックすることをお勧めします。
③現役医師が主催するゼミに参加
これに関しては、かなり特殊であまり巷にある講座ではないかもしれません。私がこのゼミに参加することができたのも偶然で、通っていた医学部受験専門塾の先生に紹介していただけたことがきっかけでした。そこでは、パワポでの発表をする機会があり、内容によって賞が贈られました。私は優秀賞をいただけたので、そのことも願書に書くことができました。またこのゼミは、とある私大に所属し活躍されている先生が主催してくださっていたので、その私大の面接ではウケが良かったように感じましたし実際に合格をいただきました。
④(医療系)ボランティア
もちろん医療系の資格を有していないので、医療行為を行うことはできませんが、医療に携わるものを含めたボランティアにいくつか参加しました。長期でできればベストでしたが、日頃の勉強もあったので単発でできるボランティアに参加しました。私が参加したのは、献血の呼びかけと案内を行うものや小中高生を支援するもの、図書館での読み聞かせです。実際に参加してたくさんの学びがありましたし、ボランティア経験を願書に記載することで、医療や社会へ貢献をしたいという強い気持ちを伝えることができます。
以上が私が、願書の対策として行ったことです。一つ一つは大きな労力がかかるものではありませんが、願書を書く時期になって始めようと思っても難しいものが多かったのではないでしょうか?一つでも参考になれば幸いです。
また、私はあまり行くことができなかったのですが、志望大学が主催するイベントへの参加なども面接や願書記入の際に好印象を残すことができると思います。実際とある私大の面接では、「うちの大学のイベントやオープンキャンパスには何か参加しましたか?」と聞かれ、少し困ってしまいました。大学に行ったことはあったのとパンフレットなどは読んでいたので、そう答えたのですが、もう少し大きなイベントに参加していた方が心象が良かったと思います。
最後に、願書に関して重要なことを二つ。
まず、できれば願書は医学部受験のプロ(予備校の担任や先生など)に添削してもらいましょう。プロでなくとも誰か別の人に見てもらうのが良いと思います。自分では気付けない間違いやより良い言い回しが見つかるものです。願書を書いたり添削してもらったりするのはそれこそ直前期なので、今回の記事のメインでは入れませんでしたがとっっても大切だと思います。自分自身、添削してもらうことで願書を他人の目から見て良いものにできたと自信を持って出願することができました。
そしてもう一つ。願書は出願開始日に出すこと。これは自分の中で、すべての大学の願書は出願開始日に出すという、ルールないし願掛けを作っていただけなのでもちろん出願受付期間なら出すのはいつでも大丈夫ではあります。もちろん願掛け以外にもメリットがあるので説明していきます。
・出願が早い方が面接の開始が早いことが多くその分終わりも早いことが多い。もちろん例外はありますが、私大受験などは人数が多いため受験番号が早い順に人数制限して受験生を帰すことがあり早い方がさっさと帰れたりするのも地味に嬉しかったりします。
・出願が早く受験番号が早い方が面接官も「この受験生はうちの大学に来たい気持ちがある」と感じやすい、と自分が思える。出願期間ギリギリに提出した人って受けるか悩んでいた可能性がありますよね。とはいえ実際、受験番号の早い遅いはあまり関係ないとも思いますが、自分がアピールできたという気持ちで面接に臨むことができることがメリットだと思います。
・〆切が決まっていると時間を無駄にしない。いつまでに出願しているか決めていないと、出願の準備は明日でいいかなどとなり、頭の片隅に願書のことがある状態で勉強することになります。その分だけ勉強への集中は削がれ、勉強効率は下がります。もちろん期間内のどの日に〆切を設定してもいいと思いますが、何事もできるだけ早い方が余裕を持って物事に取り組めます。
上記に書いたようなメリットだけではなく、デメリットやあえて最初に出願しない方が良い場合もあります。例えば、日医は出願の順番で会場が変わるのであえて遅く出してアクセスの良い会場になるようにする人もいました。また、願書を早く出しすぎると、やっぱり別の内容の方が良かったかもしれないとなることもあります。これは添削してもらうことでかなり解消できるデメリットだと思います。
ここまで色々書きましたが、要するに自分がベストだと胸張って言える日や内容で出願できれば良いです。私にとってベストな日は出願開始日でしたが、友人の中には入念に準備して暦的に縁起のいい日に出す人もいました。期日に追われるように出願したり、願書をテキトーに書いたりすると自分の中でもモヤモヤが残るものです。それは試験や面接で少なからず影響すると思うのです。出願だけでなく受験や人生そのものに言えることですが、常に胸を張れる状態で臨みたいものですね。
最後偉そうなこと言ってしまいましたが、参考になった方はいいねやコメントなど待っています。ではまた。
X(旧Twitter)始めました▶︎@ebimaru_saijyu

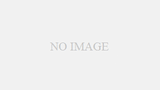
コメント